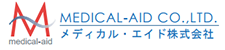メニュー(タップでメニュー表示)
よくあるご質問Q&A
- Q-01. 使用期限が約2年…使えば使うほど消耗するという認識でよろしいでしょうか。
- Q-02. 使用頻度を少なくすれば使用期限は長くなりますか。
- Q-03. 低温滅菌(EOG:酸化エチレンガス、55℃4時間)は問題ありませんか。
- Q-04. 普通の洗濯機にかけるのは可能でしょうか。
- Q-05. ミトン内側の汚れ対策で手袋等を着用しても問題ありませんか。
- Q-06. ロールシートは被せる・のせるだけでも効果はありますか。
- Q-07. 保管は毎回付属袋に戻す必要がありますか。
- Q-08. マグネットネイル等への対応:手袋等で保護できますか。
- Q-09. ミトン装着で手を体側に伸ばすと接触部が黒くなる対策はありますか。
- Q-10. 金属製の時計を付けたままミトン装着は可能でしょうか。
- Q-11. ペースメーカー装着患者はプロテクター着用で撮像可能でしょうか。
- Q-12. FreeStyleリブレはロールシートで対応可能でしょうか。
- Q-13. RFパルス過照射リスクに関する見解・データ・対策はありますか。
- Q-14. プロテクター使用中の熱感報告はありますか。
- Q-15. ミトン型MRIプロテクターの導入実績・使用件数は。
- Q-16. 2024年の低温熱傷事例:1.5Tで同様事例はありますか。
- Q-17. 頭部MRI時に四肢へ装着してもRF過照射はほとんど生じませんか。
- Q-18. 体幹撮影時、撮影範囲近くにミトン手が位置しても過照射は生じませんか。
- Q-19. ミトン型MRIプロテクターの導入実績・使用件数は。(再掲)
- Q-20. やけどリスクがある場合でもミトンが皮膚に直接触れなければ安全確保できますか。
- Q-21. 3.0Tでネイル患者:ロールシート側太腿に発疹—ループ熱以外の原因は。
- Q-22. 前腕撮像で体幹にロールシート2枚連結→腹部が熱いと申告:原因と対策は。
Q使用期限が約2年となっており、使用状況により変化すると記載があったかと思われますが、使えば使うほど消耗するという認識でよろしいのでしょうか。
A使えば使うほど消耗する認識は正しいですが、2年保証については最も使用頻度の高い毎日連続使用するケースを想定しています。
取扱説明書に記載されているとおり、汚れが付着した場合や感染症のリスクがある場合はその都度アルコール等で除菌し、毎日連続して使用する場合は月に1回程度のドライクリーニングをお勧めしております。
検査衣の上からMRIプロテクターを着用する場合は汗や汚れが裏地に付着しないので、ドライクリーニングは汚れが顕著になってからでも問題はないのですが、直接MRIプロテクターを着用した場合、汗や汚れが裏地に付着し、インサートされている電磁シールドの銀繊維が塩化・硫化して劣化が進行してしまいます。
実際に2年近くクリーニングしなかったケースの1件で規定以下の性能劣化が認められました。
Q極端な話、使用機会を限定するなど使用頻度を少なくすれば、使用期限は長くなる可能性があるということでしょうか。
AMRIプロテクターを共同開発いたしました住友病院様ではほぼ毎日使用していますが、3年経過後も問題なく使用できております。取り扱い方法を間違えなければ使用期限は長くなります。
メーカー保証期間終了後には当社から保証期間終了のご案内を差し上げますが、実際の撮像画像でMRIプロテクターを着用した部分がうっすら見えるようになってきてから交換しても問題はないかと存じます。その場合は自己責任でのご使用をお願いしたいと存じます。
Qメンテナンスの種類に低温滅菌(ガス滅菌)とありますが、病院で可能なものがEOG滅菌(酸化エチレンガス滅菌)のみで、55℃ 4時間の滅菌工程です。問題ございませんでしょうか。
A100℃以上の高温滅菌以外は問題ございませんので、記載いただいているEOG(酸化エチレンガス)滅菌を行っていただいて問題ございません。
Q普通の洗濯機にかけるのは可能でしょうか。
A洗濯機のご使用については、インサートしている金属繊維(電磁波遮蔽材MGネット)が劣化して性能が落ちる可能性がございますので、石油系ドライクリーニングをお勧めしております。
メンテナンス時期については汚れた場合はその都度、毎日連続して使用する場合は最低でも月に1度はメンテナンスを行っていただきますようお願いいたします。
Qミトンの内側(肌に触れる部分)の汚れ対策に手袋等を着用しても問題ありませんか?
A問題ございません。装着後は開口部を絞ってすき間をなくし必ずストッパーで封止してください。
Qロールシートは患者様に被せる・のせるだけでも効果はありますか?
A効果は多少はありますが巻き付けてすき間を無くす方が良いです。シートタイプは何周巻き付けても異常はありません。
Q保管方法は製品の入っていた袋にその都度保管する必要がありますか?
A毎日使用される場合はハンガー等にかけておいても問題ありません。使用頻度の高い病院様でもハンガーにかけた状態で3年経過後も問題なく使用されています。長期間使用されない場合は、お手入れ後に納品時に封入しておりました気密袋にて保管ください。
Q最近ネイルアートに使用されるマグネットネイルや一部のジェルネイルに磁性体のモノが使用されMRI検査が出来なくなっており困っています。これを回避するために、磁場の変化やRFから手を守る手袋などはありますか?
Aマグネットネイルに使用される砂鉄の質量は小さくさらに表面をコーティングしているため吸引については問題はございません。ジェルネイルに含まれる砂鉄は磁性を帯びた金属成分ですのでMRI撮像時の発熱・変色のリスクは考えられますが、ミトンを装着することで発熱や変色のリスクを低減することができ、ネイルを取ることなく撮像が可能です。これまでの臨床使用や実際に購入された病院様で、マグネットネイルを含む金属製のネールアートや指輪や手首の固定具などにミトンを装着し問題なく撮像されております。このような使用でトラブルがあった事例は4年間で0件です。同じような目的でミトンを導入されている病院様が現在増えてきております。
Qミトンを装着して手を体側に伸ばした状態で撮像を行うと、他の箇所(ミトンが当たるところ)も黒くなり撮像できないことがありましたが対策方法はありませんか?
A太腿と手の間にクッションなどを挟み5㎝程度の隙間をあけることをおすすめいたします。また、たとえば股関節や大腿部、骨盤を撮像する場合(胸部の撮像をされない場合)は手を胸の方に置いていただくとよろしいかと存じます。挙上する必要はございません。
Q金属製の時計を装着したままミトンを装着しても良いでしょうか?
A基本的に非磁性金属であればミトンを使用すれば問題はありません。時計に関しては電磁波の影響より強い磁場の影響が懸念されるので、外す方が良いかと存じます。指輪やネイルは外せないケースでミトンを使用すれば安心して使用可能です。
Qペースメーカー装着患者様はMRIプロテクターを装着すれば撮像可能でしょうか?
A弊社では理論上はペースメーカを植込みされていても問題はないと考えております。 ペースメーカの設定をオフにしていれば影響が出ることはまずありません。しかし、実際の臨床を実施しておりませんので、現状ではMRI非対応のペースメーカーに対する安全は保証できません。しかしながら、MRI対応のペースメーカーであってもMRIプロテクターを使用することでリクスは低減されます。また、MRI対応のペースメーカーであっても3TのMRIは使用しないケースが多いので、3Tを使用する場合はMRIプロテクターの着用を推奨できます。
Qぺースメーカー以外の装着機器について、24時間リアルタイム血糖測定装置(アボット社 FreeStyleリブレ)は、現状MRIなどの検査前に外す必要がありますが、ロールシートタイプで対応可能と考えて良いでしょうか。
AFreeStyleリブレ自体の測定を過去に行った事例はございますが、MRI撮像時の検証ではございません。リブレ取扱説明書よりリブレに影響を及ぼす電磁ノイズは、電源周波数(50/60Hz)変動磁界では30mA(37.7μT)、放射RF(80M~2.7GHz)では10V/mとされていますので、MRI検査前には取り外す必要があります。
QMRI安全関連の専門サイト「MRISAFETYFORUM」にて、「RFパルスの照射野内にプロテクターを配置した場合、人体からの反射波が得られず、覆われていない部分に対してRFパルスの過照射が生じる可能性があり非常に危険である」との記述がございました。MRI装置メーカーに問い合わせたところ、撮影する範囲以外にもRFパルスは照射されるということでした。RFパルスの遮蔽についてはデータがあるようですが、このような見解について、貴社として何かデータなどありますでしょうか?また、このリスク(あればですが)に対してどのような設計的または運用上の対策を講じておられるのでしょうか?
A■RFパルス遮蔽と安全性に関する弊社の見解:
MRIプロテクターは、RFパルスを完全に遮断するのではなく、効果的に減衰させることで金属の誘導加熱を抑制する設計です。試験では、着用時にRF信号を平均で80%以上減衰させることが確認されております。
試験データはこちら↓ https://www.medical-aid.co.jp/pdf/MRIreport01-shield.pdf
Z軸方向(頭-足方向)の磁束に関しては、構造上、襟元や裾など完全な遮蔽が困難であるため、一部のRF波がプロテクター内部へ進入する可能性がございます。ただし、画像上で測定した結果、腕・膝・大腿部などへのロールシート巻付時、Z軸・−Z軸ともに3~5cm程度の信号入力が認識され、徐々に減衰していることが確認されています。したがって、金属部の末端から5~10cm程度を覆うことが推奨されます。
■ RFパルスの「加照射」リスクについて:
RF波はRF送信チャネルによりガントリ内へ均一に送信されており、メーカーによって制御方式に違いがあります。プロテクターで覆われた部位はRF信号が遮蔽され、MR信号が受信チャネルに適切に入力されない場合、スキャン停止やSAR(比吸収率)の上昇が生じる可能性があります。この点は製品の取扱説明書にも明記されており、加照射のリスクについても留意が必要です。例として、大型のボディコイルを使用し右腕を撮像する際に、胴体へプロテクターを装着していると、再構成に必要なプロトン数が不足し、スキャンが停止する可能性があります。
対応策としては:
小型サーフェイスコイルを使用し、腕に巻き付けて撮像
撮像範囲に硫酸銅ファントムを配置しスキャンを維持
患者のポジショニングを工夫し、腕を挙上して撮像
などの運用上の工夫が有効です。
■ 使用にあたっての原則:
施設の方針によりますが、未確認の体内デバイスの有無を明確化し、MRI非対応のペースメーカ等禁忌デバイスには原則として使用不可とするべきです。また、MRI検査に際し、MRIプロテクター使用に関する事前の同意書も推奨いたします。
Qプロテクター使用中に熱感を訴えるケースがあったと聞いていますが、実際にそのような報告はありますか?
A2024年に1件、ミトン型MRIプロテクター使用中における低温熱傷の事例が報告されております。
本件は、大阪府薬務課・厚生労働省・PMDAへ報告済みであり、製品の回収は不要と判断されました。詳細は以下の報告書をご参照ください。
▶ 報告書(PDF)↓
https://medical-aid.co.jp/pdf/mrimitton-casereport202503.pdf
Qミトン型MRIプロテクターの導入実績や使用件数について教えてください
A導入施設:以下のページにて導入実績を一覧で掲載しております。
▶ 導入事例一覧 https://www.medical-aid.co.jp/products/clothing/mriprotector/jirei.html※使用後の感想もページ末に記載しています。
▶ 使用件数:過去6年間で1000件以上の使用実績がございます。
Q2024年の低温熱傷の事例について、発生頻度は低いかと存じますが、1.5TのMRI装置において同様の事例が報告されたことはありますか?
Aこれまで1.5TのMRI装置において同様の事例が報告されたことはございません。 1.5T(64MHz)と3T(128MHz)装置は静磁場強度の違いから共鳴周波数が異なりますが、高周波ループに対する安全対策に違いはありません。
Q頭部MRI検査において肩、手、足などにプロテクターを装着した状態で撮像してもRFパルによる過照射はほとんど生じませんか?
AこれまでSAR上昇したという報告はありません。RFパルスによる過照射はほとんどないと考えます。
Q腹部や腰椎など体幹部の撮影を行う際に、撮影範囲付近にミトンで覆った手が位置していても、RFパルスによる過照射は生じないという理解でよろしいでしょうか。
ARFパルスの過照射は、体位、撮像方向、パルスシーケンスの撮像条件によって過剰に照射される可能性があります。 したがって場合によってSARが上昇することがあります。
Q仮に火傷のリスクがある場合でも、ミトンが直接皮膚に接触しないように配慮すれば、安全性は確保されると考えてよろしいでしょうか。
Aミトンの有無にかかわらず、高周波電流ループによるやけどのリスクがある場合は手と足などの接触は禁忌なので、クッション材を入れるなどして安全を確保してください。 ミトンを装着した手はやけどのリスクは回避できても、接触した足はやけどのリスクがあります。
Qマグネットネイルをした患者様に対して、3.0TのMRI装置にて検査を実施した際に、
片手にミトン、もう片手にロールシートを装着して腰椎部分の撮像を行った時に、ロールシートを装着した手をおろしていた太腿の所に、赤い発疹ができた。(検査着は着用していた)
また、患者様も手が熱くなってきたが、ブザーは持っておらず、我慢できるレベルだったのでそのままの状態で撮像を行った。
今までも同様の検査方法でネイルをした患者様に使用していたが、今回のようなことは起こったことがないのですが、
このような場合、ループ熱以外に何が考えられますか?
A今回のケースはMRIプロテクターが原因の発熱ではないと思われます。
本件の原因は、ロールシートを巻いた腕と太ももの間に高周波電流ループ形成され、誘導電流が流れ、ロールシートの袖口と太ももの間の抵抗の大きい部分にジュール熱が発生したことが原因です。
MRI検査でいかなる部位を撮像する場合(プロテクター使用の有無に関わらず)ループ形成することが無いようクッションやタオルなどを挟む、長袖長ズボンの検査着を着用するなど対策を施さなければなりません。
ロールシートに守られていた手は熱く感じたが発疹まで至らなかったが、ロールシートの口と接触した太もも(検査着着用であったがMRIプロテクターは不使用)に熱による発疹が出たと考えられます。
今回のケースでもしロールシートがなかった場合は、手と太ももの接触による高周波電流ループでもっとひどい熱傷が起きた可能性があります。
MRIプロテクターのミトンやロールシートを使用した状態で腰椎や骨盤部を撮像する場合でもループ対策は同様です。
上腕前腕と体幹の間、プロテクターと体幹の間、太ももの内側の皮膚接触、両下腿内側の皮膚接触、足と足の内側の皮膚接触、またガントリと皮膚接触も注意しなければなりません。
MRIプロテクターに守られている体内および体表金属のある部位は、高周波電流ループによる発熱やガントリ接触による発熱を電磁波シールド素材が逃がしてくれるので、やけどに至る可能性は低くなります。
万が一高周波電流ループやガントリ接触に備えて、MRIプロテクターを使用していても検査着は少し厚手のものを使用した方が安全です。
また、緊急連絡用ブザーは意思疎通が取れる患者へは、必ず少しでも熱さを感じたときは使用するよう説明したうえで手渡した方が良いかと存じます。
Q肘から下の前腕部の撮像時、体格が大きい患者だったため、検査着の上から腹部にロールシートBを巻いたところ長さが足りなかったので、2枚繫げたような状態で巻いた。MRIの機器に対して真ん中に撮像部位の前腕部がくるように、患者をボアの端側に寄せて寝かしたところ、撮影後、プロテクターを巻いた腹部だけが熱くなったと申告された。
- ・目的は折り返しアーチファクト対策
- ・体内に金属等はなし
- ・MRI フィリップ社製 3.0T使用
- ・コイルは、普段手の撮像の際は小さいものを使用するが、今回は大きいもの1枚を体に乗せた状態だった
A以下の回答となります。
- 1)背景・前提
- 本プロテクターは、体幹撮像時に腕部の折り返しを抑制する等を想定した設計で、今回のように前腕撮像で体幹側を広範に遮蔽する使い方は、設計意図と逆方向の運用になります。 施設・装置によっては、この運用でロカライザー/本スキャンが開始できないことがあります。Philips 3.0Tは MultiTransmit やコイル側AD変換等の特性により、低SNR環境でも撮像が成立した可能性がありますが、SARの上昇を招きやすい状況になっていたと推測されます(あくまで仮説)。
- 2)熱感の主な原因仮説
-
- • (A) ループ形成 体幹—ガントリ接触、体幹—上肢、両大腿などで導電ループが形成されると誘導電流→発熱が起こり得ます。プロテクター装着時でも、クッション等で確実に絶縁・スペーシングを行わないと発熱のリスクが残ります。
- • (B) RF送信の過補償によるSAR上昇 体幹を広く遮蔽すると受信信号が不足し、装置側が送信制御を強める方向に働き、局所SARが上がる可能性があります。
- • (C) ロールシート2枚の連結による重なり・端部(導体端・重なり部)は電界集中(ホットスポット)を生じやすく、局所加温の一因となり得ます。
- • (D) 材料の経年劣化(保証期限を越えた製品の場合) 経年劣化による銀メッシュの酸化等で抵抗上昇→蓄熱傾向となる可能性があります。 補足:当社の内部試験では、RFは完全遮断ではなく減衰させる設計で、平均遮蔽率80%以上を確認しています。Z軸方向へのRF侵入は3–5 cm程度画像上で認められるため、金属末端から5–10 cmの余裕をもって被覆することを推奨しています。
- 3) ご質問への個別回答
- • プロテクター装着が熱さの原因になり得るか? なり得ます。とくに(A)(B)(C)の条件が重なるとリスクは上がります。
- • 巻き方に原因があったか? 可能性が高いです。2枚連結・重なり部の処理、体幹の全周近い被覆、クッション未介在によるループ形成など、巻き方・固定法が影響したと考えます。
- • 避けるべき使用法 設計意図と逆の「前腕撮像のために体幹を広く遮蔽」は原則推奨しません。やむを得ず行う場合でも、ループ対策・連結部処理・SAR監視を厳格に行ってください。
- 4) 実務上の推奨代替策
- • 小型サーフェスコイルで前腕局所を撮像する
- • 撮像場の維持が困難な場合、硫酸銅ファントムを近傍に配置してスキャン安定化を図る
- • ポジショニング:腕の挙上などで体幹から距離を取り、ループ形成を避ける
- • 体幹側に広範なプロテクターを巻くのではなく、目的部位周辺のみ最小限の使用とし、端部の重なり/閉ループを作らない
- • クッション・フォームで絶縁(体幹—ガントリ、四肢—体幹、両下肢間など)
- • SAR・装置警告のリアルタイム監視、患者への熱感ヒアリング、違和感時の即時中止
今回の熱感は、 ①ループ形成対策の不十分、②連結重なり・端部処理、③逆方向の運用に伴うRF送信増加(SAR上昇)、④経年劣化が複合して生じた可能性があります。 折り返し対策として体幹を広く遮蔽する方法は原則避け、コイル選択・ポジショニング・ファントム活用での対処を第一選択としてください。 プロテクター使用時は、非閉ループ化とスペーシングを徹底し、端部の重なりを作らないことが重要です。
ご購入のご案内
▼お電話でのお問い合わせはこちら▼
TEL 0725-53-3270
※番号のお間違えのないようにご注意ください。
●受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(年末年始および祝祭日除く)